オブザーバビリティメトリクスの分析に生成AIを活用

Observability CloudのAI Assistant (2024年6月執筆時点ではプライベートプレビュー版1を提供、現在は一般提供)は、オブザーバビリティ(可観測性)のデータソースとワークフローを自然言語で操作するためのインターフェイスを提供します。SignalFlowは、Splunk Observability Cloudの中核をなす分析エンジンであり、リアルタイムのデータ処理とメトリクスの分析を目的として設計されています。また、プログラミング言語やライブラリなどのコンポーネントも備わっています。これにより、大量の受信データストリームに適用できる分析処理をコーディングし、メトリクス、チャート、ディテクターの形でインサイトを提示することが可能になります。関連するブログ記事では、AI Assistantの設計思想とアーキテクチャの概要、特にエージェントを用いた設計パターンをオブザーバビリティの分野にどのように適用したかについて詳しく説明しています。このブログでは、大規模言語モデル(LLM)を使用してSignalFlowプログラムを生成する際の課題と方法について重点的に取り上げます。
SignalFlowはPythonの文法をモデルとしており、データの取得、出力、そしてアラートを生成するための組み込み関数を備えています。まず、簡単なSignalFlowプログラムの例を見てみましょう。
data('cpu.utilization',
filter=filter('host','example-host')).mean(over='5m').publish()
このプログラムはまず、「cpu.utilization」メトリクスのフィルタリングされたデータポイントのセットを取得し、「host」ディメンションが「example-host」と一致するデータポイントのみが処理対象となるようにします。次に、ストリーム内のデータポイントの平均を計算し、5分間のローリングウィンドウの平均を算出します。最後に、publishブロックによって分析システムに結果を出力するよう指示しています。なお、Function Callingとメソッドチェーンは、Pythonでの動作と同様です。
課題と方法
生成AIにおける課題の中でも、特に困難なのがコード生成です。なぜなら、たった1文字の誤りでも構文エラーを引き起こす可能性があるからです。SignalFlowのようなニッチな言語のコード生成は、さらに大きな挑戦を強いられます。その理由として、SignalFlowに関する知識を持つモデル(オープンソースかクローズドソースかを問わず)が非常に少ない、あるいはSignalFlowの知識を持っていたとしても、Pythonに関する情報が混入することで、その知識が劣化してしまう場合があることが挙げられます。したがって、コードを生成するためにファインチューニングされたモデルであっても、品質の高いSignalFlowのコードを生成するには、さらなるカスタマイズが必要となります。
特定のタスクに合わせてLLMの生成を調整する手段として、追加の例を使用してモデルの性能を強化する方法があります。これは通常、入力と出力(質問と回答、文章とその翻訳など)のペアの形式になります。プロンプトには、入力と出力との一般的な関係性を記述し、可能であれば例もいくつか含めます。この際に使用できる検索拡張生成(RAG)という洗練された手法があり、これによって、入力内容に応じた適切な例をプロンプトに含めることができます。一般的な実装では、ユーザーのプロンプトを基にデータソースに対してセマンティック検索を通じて類似度を評価し、取得した中から関連性の高い例をいくつか選んでプロンプトに含めます。このアプローチは、コンテキストと関連性の高い情報を提供することによってモデルの応答を強化します。これに加え、ファインチューニングを行うことでモデルをさらに強化します。ファインチューニングは、追加の例でモデルをトレーニングし、内部の重みを調整して目的のタスクへの習熟度を高めます。RAGは入力トークン数の増加により計算コストが高くなる可能性があります(例がプロンプトに追加されるため)。一方、ファインチューニングは初期段階で多大な労力を要するものの、タスク固有の知識をモデル自体に組み込むことで長期的なメリットが得られます。RAGとファインチューニング、いずれの場合も大規模かつ多様で高品質な例のセットが必要となります。
データのキュレーション
ユーザーの環境に関する質問(例:「“example-host”の過去5分間の平均CPU使用率は?」)を解釈するために、まずすべきことは英語の質問とそれに関連するSignalFlowプログラムの両者を組み合わせたデータセットを厳選することでした。これは、次の図に示す多段階のプロセスによって実現しました。つまり、データの収集と前処理、SignalFlowプログラムの分解、タスクの指示と質問の生成、品質のスコアリング、そして最終的な質問と回答のペアの作成です。
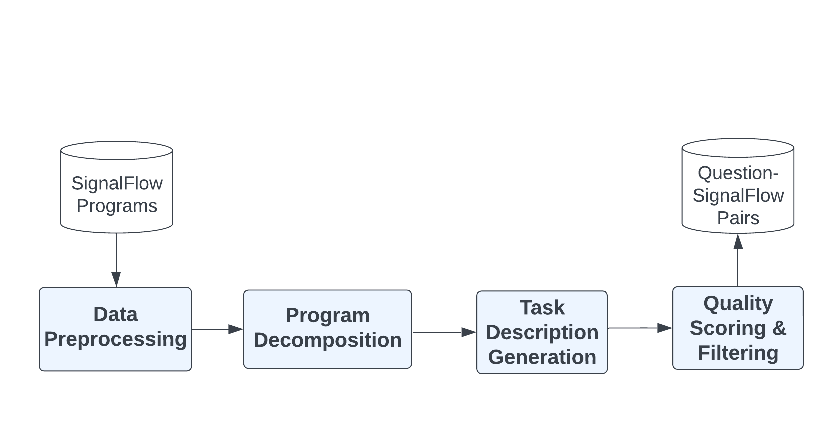
図1:データのキュレーションの手順
- データの収集と前処理:社内のSplunk O11y Cloudの利用実績から多数のSignalFlowプログラムと、それに付随するチャートのタイトルや説明などのさまざまなメタデータも収集しました。また、前処理の段階で、機密情報(カスタムメトリクス名や組織情報など)の匿名化やマスキングを行いました。すべてのプログラムがSignalFlow構文検証ツールに合格し、構文エラーなしで実行されることも確認しています。
- SignalFlowプログラムの分解:社内プログラムの多くは非常に複雑で、人間による多段階の推論で構成されています。モデルにとって有用な構成要素を抽出するために、LLMを使用して複雑なSignalFlowプログラムを独立したユニットに分解しました。各ユニットは、それ自体が実行可能なプログラムになる必要があります。LLMにチャートの説明、チャートのタイトル、メトリクスのメタデータを与え、SignalFlowプログラムをユニットに分解するよう指示しました。各ユニットは、元のプログラムのいかなるコード行からも独立していなければなりません。分解が完了したら、モデルに分解結果を評価するよう指示し、スコアの低いものを除外しました。残りのユニットについては、構文の正確性を検証しました。
- タスクの説明の生成:SignalFlowプログラムのタスクの説明を生成するために、2段階のアプローチを使用しました。これを通じて、分解によって抽出されたユニットにタスクの説明を付与します。
- タスク指示の生成:まず、LLMにタスク指示を生成するようプロンプトしました。これにより、SignalFlowのプログラミングタスクの理解と解決に役立つ詳細が提供されます。LLMがより具体的でわかりやすい説明を生成できるよう、元のSignalFlowプログラムおよび有益なコンテキストも与えました。
- 質問の生成:次に、このタスク指示、SignalFlowプログラムとコンテキスト情報も併用して、LLMへのプロンプトを通じて、英語の質問を生成させました。具体的には、ユーザーが現在のタスクを解決するために尋ねそうな、カジュアルな質問と詳細な質問の両方を生成するようプロンプトしました。カジュアルな質問は、実際の場面でユーザーが尋ねるであろう質問の内容に近いため、RAGとファインチューニングに適していると判断しました。
- カジュアルな質問:「各Load Balancer-APIインスタンスにはどれくらいの空きRAMがありますか?」
- 詳細な質問:「Load Balancer-APIの各インスタンスのメモリ使用量をモニター、測定、レポートすることで、使用可能なRAMまたは空きRAMの割合を正確に計算できますか?」
- 多様な質問群を確保できるよう、我々はLLMに対してプロンプトを渡し、同じタスクに対して、結果的に同じプログラムが生成されるような質問を数多く生成させました。これにより、さまざまな切り口や表現パターンを網羅したデータを確保でき、RAGの過程で関連性の高いQ&Aペアを取得できるようにしました。
- 品質のスコアリング:その後、モデルに「self-reflect (自己反省)」を指示し、これらの質問の複雑さと多様性をスコアリングして、スコアの低い質問を除外しました。これは、すべての質問が“Ground Truth”プログラム(正解を答えるプログラム)に、一定の水準以上で一致するようにすることを目的としています。
この手順により、各例が、カジュアルな質問、詳細なタスク指示、SignalFlowプログラムで構成される、数万例からなる厳選されたデータセットが作成されました。
SignalFlowの生成アーキテクチャ
自然言語からSignalFlowモデルを作り上げるには、上記で作成したデータセットを中心に構築していく必要があります。この基本構成要素となるのは、SignalFlow生成を担当するエージェント(サブLLM)のプロンプトを渡す機能、ユーザー固有のメトリクスとメタデータを取得するためのメカニズム、プログラム検証機能(検証失敗時のエラーメッセージ表示を含む)です。現在の実装では、データセットはRAGを介してエージェントのワークフローに取り込まれます。
ユーザーからの質問を受け取ると、オーケストレーターLLMは、回答を提供するためにメトリクス検索が必要かどうかを判断します(ユーザーがメトリクス名を指定していない場合がこれに該当します)。適切なツールを呼び出してメトリクス名とそのメタデータを取得しますが、その際には、ユーザーの質問から検索語句を抽出する必要があります。それから、最初のユーザーの質問、メトリクス名、メトリクスメタデータをSignalFlow生成サブLLMに渡します。ワークフローを以下に示します。
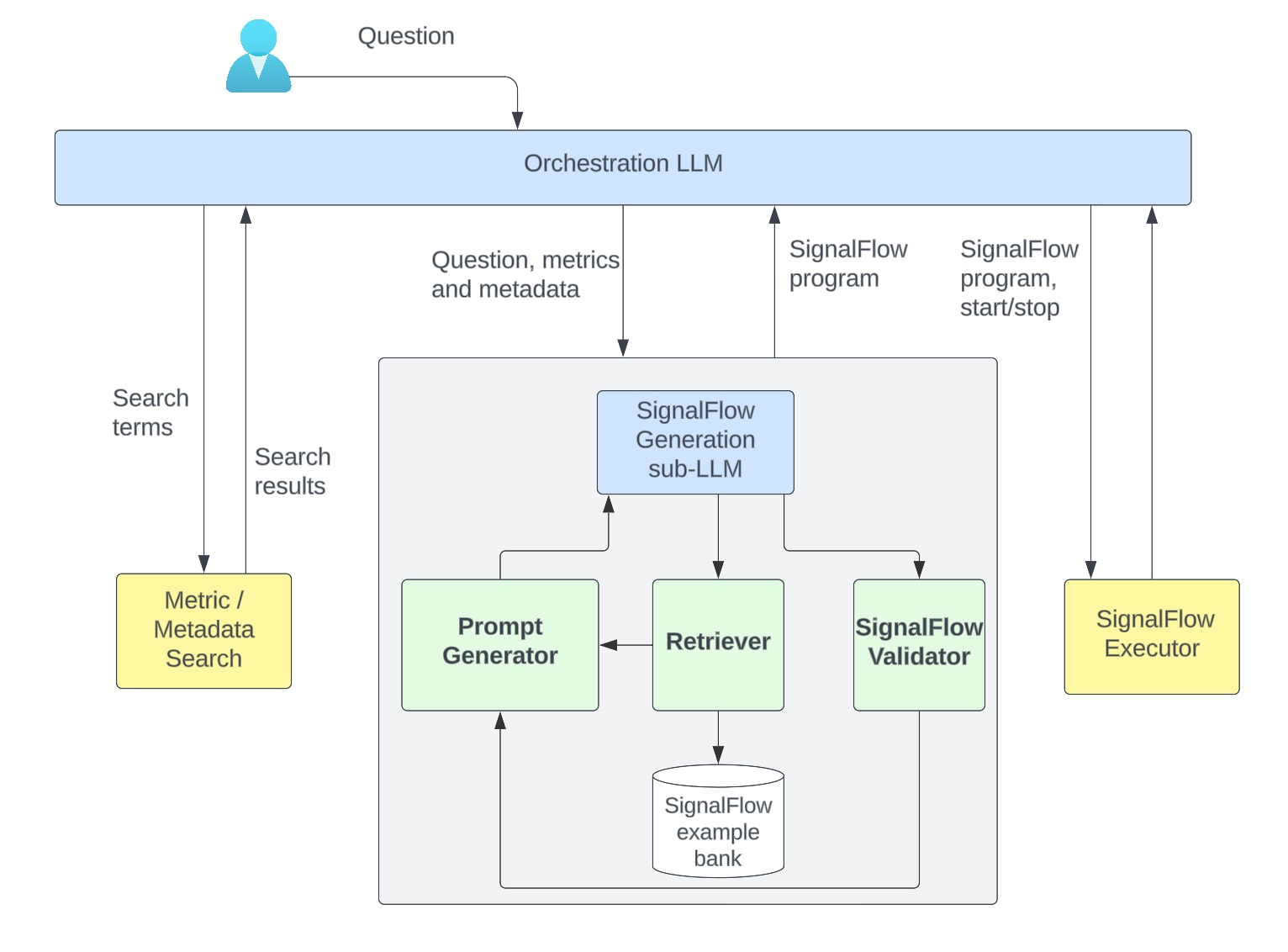
図2:SignalFlow生成プロセスの全体的なフレームワーク
SignalFlow生成サブLLMは、質問を受けてからSignalFlowプログラムを生成するまでの全工程の調整を担います。その特徴は、自然言語による質問とメタデータコンテキストを受け取り、質問に答えられる完全なSignalFlowプログラムを生成する点にあります(提供されたメタデータコンテキストは、必要に応じてプログラム内で使用されます)。システムプロンプトには、SignalFlowプログラムの重要なコンセプトと構成要素に関する説明と例が含まれています。主なコンポーネントは次のとおりです。
- Prompt Generator:元の質問、関連するメトリクスとメタデータ、取得した例、構文検証フィードバックから、LLM入力(プロンプト)を作成します。
- Example Bank:厳選された質問とSignalFlowのペアからなるデータセットで、ベクトルインデックスとしてまとめられ、データ検索のメカニズムを備えています。このExample Bankから最も関連性の高い例が取得されます。具体的には、ユーザーの質問を、厳選済みのペアの質問と同じベクトル空間に埋め込み、コサイン類似度を使用して上位k個の最も近接した質問とSignalFlowのペアを見つけます。ここで取得された例がプロンプトに挿入されます。
- SignalFlow Validator:候補プログラムの構文の正確さをチェックします。SignalFlowプログラムの検証に合格した場合、サブLLMはそれをオーケストレーターに返します。通常、その後オーケストレーターがプログラムの実行へと進みます。検証に失敗した場合、エラーメッセージがサブLLMのコンテキストに追加され、サブLLMは数回再試行します。
評価
生成されたSignalFlowプログラムの正確性を評価することは容易ではありません。なぜなら、与えられた質問に対して複数の正解(プログラム)が存在する可能性があるためです。したがって、サブLLMのパフォーマンスの全体像を把握するには、いくつかの評価メトリクスを使用します。
- ベクトル埋め込みに基づく類似度を使用して、生成プログラムと正解プログラムがどれだけ近いかを測定します。大きく異なって見えるプログラムでも、意味的に類似していることがあるため、そのような場合はこの方法が有効です。ただし、SignalFlow固有の構造を十分な精度で解釈できる埋め込みモデルを選択できるかどうかが課題となります。
- 手動で数多くのプログラムのペアを比較するのは困難で時間がかかるため、LLMベースのスコアも活用します。評価用LLMモデルにユーザーの質問、生成されたプログラム、正解プログラムをプロンプトし、生成されたプログラムをさまざまな要素(使用されている関数、ユーザーの元の質問との関連性、簡潔さなど)に基づいて評価し、そのスコアリングの正当性を説明するよう指示します。このアプローチの成否は、明確なスコアリングルールを提示できるかどうかに大きく依存します。開発の方針を定め、生成AIの潜在的な弱点を特定する上で最も有益な出力情報は、評価用LLMによる説明です。モデルが2つのプログラムの違いと、その違いが与える影響度に関する説明を提供することで、人間の手動による評価作業が大幅に軽減されます。これは、プログラムについての私たちの理解と評価用LLMが提供した説明内容を相互参照できるようになるからです。また、評価用LLMのフィードバックを確認し、パターンを理解するだけで、サブLLMのSignalFlow生成機能のどの部分に弱点があるかも容易に知ることができます。
SplunkのサブLLMベースアプローチによるモデルは、いずれの指標についても、主流のSignalFlow対応モデルの性能を大幅に上回っています。さらに、私たちのアプローチは、一貫して高い構文品質を持つSignalFlowプログラムを生成するという点においても優れた性能を示しています(1,000個のプログラムで99%以上の検証成功率)。これは構文検証のフィードバックループが功を奏していると言えます。この実証テストの結果は、Splunk社内の事例証拠とも一致しています。他のLLMベースのチャットボットが有効な支援とならない状況で、AI Assistantが中程度の複雑さを持つ正確なSignalFlowプログラムを生成できた事例が多数確認されています。
まとめ
SignalFlowプログラムを作成可能な生成AIの構築には、さまざまな側面において技術的改善が求められました。高品質な質問とプログラムのペアの厳選、RAGと検証ツールにより生成されたコードの意味および構文の正確性の確保、半自動化された評価ツールの作成などです。SignalFlow生成サブLLMを通じて、Observability CloudのAI Assistantの機能向上を図るとともに、将来の機能強化の基盤も築くことができました。今後の展望としては、RAG技術の強化、評価パイプラインの改善、ユーザーフィードバックの統合を通じて、SignalFlow生成機能を強化する方法を探っていくことを予定しています。
オブザーバビリティテクノロジーの最前線に立つSplunkは、こうした進歩を支える強固なプラットフォームを提供し、監視と分析における継続的なイノベーションとユーザーエクスペリエンスの向上を約束します。これからも、お客様からのフィードバックと進化するテクノロジーを原動力に、AI Assistantの改良を続けていきます。
1 Observability CloudのAI Assistantは、Splunkに事前に承認を得た一部のプライベートプレビュー参加者にご利用いただけます(2024年6月執筆時点)。
2 LLMの「self-reflection(自己反省)」機能については、現在も研究と議論が続けられています。「Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning」や「Large Language Models Can Self-Improve」といった論文では、自己反省の考え方を支持する見解が示されています。当社では、LLMにスコアリングを行わせ、そのスコアの低いものを除外する方法を選択しました。これは、生成されたデータを高品質として手動でラベル付けするための後続の選定作業において、LLMに実行させた自己反省の結果が役立つことが実証されたためであり、前述の議論のいずれかの立場を支持しているわけではありません。自己反省の機能は、英語の質問とSignalFlowプログラムのペアからなるデータセットを生成するという特定のタスクにおいて、生成されたペアを除外するための便利な方法として使用されたものであり、その他のペアをデータセットに含めることを正当性する根拠としているわけではありません。
このブログ記事の共同執筆者をご紹介します。
- Om Rajyaguruは、Splunkのアプライドサイエンティストで、主にマルチエージェントLLMシステムの設計、ファインチューニング、評価に取り組むとともに、時系列クラスタリング問題にも携わっています。2022年6月に応用数学と統計学の学士号を取得し、研究ではディープニューラルネットワークのマルチモーダル学習と低ランク近似法に焦点を当てていました。
- Joseph Rossは、Splunkのシニアプリンシパルアプライドサイエンティストを務めており、オブザーバビリティ分野の問題にAIを応用する研究に取り組んでいます。コロンビア大学で数学の博士号を取得しています。
- Akshay Mallipeddiは、Splunkのシニアアプライドサイエンティストです。主にObservability CloudのAI Assistantの拡張に取り組んでおり、大規模言語モデルに不可欠なデータ統合の側面を改善するための戦略を策定しています。また、大規模言語モデルのファインチューニングにも携わっています。ニューヨーク州ストーニーブルック大学でコンピューターサイエンスの修士号を取得しています。
- Kristal Curtisは、Splunkでプリンシパルソフトウェアエンジニアとして、エンジニアリングとAIサイエンスを組み合わせたプロジェクトに取り組んでいます。いずれも、AIをSplunk製品に統合し、より使いやすく、ユーザーのデータやシステムに関するより強力なインサイトを提供することを目指しています。Splunkに入社する前は、カリフォルニア大学バークレー校でコンピューターサイエンスの博士号を取得し、RAD & AMPラボでDavid Patterson氏とArmando Fox氏とともに研究していました。
協力者への謝辞:
- Liang Gouは、SplunkのAI担当ディレクターとして、オブザーバビリティとエンタープライズアプリケーションを主軸とした生成AIイニシアチブに取り組んでいます。ペンシルベニア州立大学で情報科学の博士号を取得しています。
- Harsh Vashishtaは、Splunkのシニアアプライドサイエンティストを務めており、Observability CloudのAI Assistantに携わっています。メリーランド大学ボルチモア郡校でコンピューターサイエンスの修士号を取得しています。
- Christopher Lekasは、Splunkのプリンシパルソフトウェアエンジニアであり、Observability CloudのAI Assistantの品質責任者を務めています。スワースモア大学でコンピューターサイエンスと経済学の学士号を取得しています。



